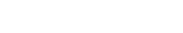コンデンサ
演習問題解説
a・b・c:標準問題
d・f:難問
e:あまり見かけないタイプの問題で、
出題されると戸惑う可能性がある問題
全体的に難易度は高めですが、
基本的な解法の流れは共通しています。
すべての問題に対応できるようになれば、
回路を除いたコンデンサの分野に関しては
十分な実力がついたと言えるでしょう。
a.

直接解答する問題ですが、
忘れることもあるので、
Qを置いて導けることが
大事です。

今までのように、Qを分けて
計算してもよいですが
上記のことは利用したほうが
効率的なので
利用していきましょう。
理由は今まで、
やった問題にあります。
外側の電場=0なので、
大外の電荷=0です。
向かい合う電荷は
大きさが同じで±になります。
この状況で、Eの大きさになります。

大外電荷=0
向かい合う電荷の大きさ同じを利用すると
図の電荷の状況になります。
BとCの電荷の和=0は
問題に書いてあります。
これにより、
BとCの間の電荷もわかります。
極板間の電場は全部
QDによるものになり
同じ大きさになります。
電圧 = 電場×d×3
よりQDが求まり
全部求まります。

Sw1を開く⇒
DとAの電荷は変わらない
事になります。
Sw2閉じる⇒
CとBの電位が同じ⇒
CとBの間の電圧0
電場の大きさ=0⇒
CとBの間の電荷=0
になります。
DとC,
AとB間の電荷の大きさは同じ
なので、
電荷の状況がわかります。
ほぼ
計算せず終了です。

Sw1を閉じ電圧Vにするので、
AとDの電荷は新しく
なります。
外側=0
中側は大きさ同じです。
Sw2開く⇒
BとCの電荷は変わらない事になります。
注意としては、
Bの電極の上と下の
割合は変わります。
あくまで和が変わらない。です。
CとBの外側は確定します。
CとBの内側は不定になるので
新しく電荷を建てます。
電場の大きさが決まるので
同じように
電圧=各電圧の和より
関係式ができます。
電荷保存の式と組み合わせて
電荷を求めます。

電荷がわかっているので
計算問題です。
U = 1/2QVで求めます。
電気容量は3つとも同じなので
U = Q^2/2C
でも良いです。
間違えないように計算します。
途中
Q" = 4qがありますが
計算式を見て代入しました。
そのまま気にせず
やっても問題ありません。
このような問題を抵抗なく
計算し全問正解することを
目指してください。
20点分ぐらいあるので
結構大きい配点です。
b.

bにQ,aに―Qとし、
スイッチすべて開いて、
a-b間の電気容量Cを
まず求める。

SW2を閉じると、
閉じた電極は
等電位になり、
等電位の間の
電場=0になります。
電圧を求めて
電気容量を求めます。

Sw1,Sw2を閉じ、
aの等電位を赤
bの等電位を青
とする。
(電位青-赤)を電圧Vと
すると、
図の電圧状況になります。
極板間d、電圧Vが
すべて同じなので、
電場も同じ
電荷も同じ。
Vの電荷を求め、
bの電荷Qは3個分より
電気容量が求まります。
c.

電荷を求めます。

電源はずすと
電荷は同じです。
真空の電場は変化しません。
誘電体内の
電場が変化します。

電位=Exで求まります。
0 < x < d/2の時
E = E2
d/2 < x < dの時
E = E1
でグラフを描きます。

再び、Vにして
電荷をQ1として
電場から電圧を求めます。
Q1を求めます。

誘電体の電荷をQA
真空の電荷をQBと
します。
電源をはずすと電荷は変わらないので
Q = QA+QBです。
左右の電圧は同じなので、
左右の電場の大きさは同じになります。
この条件から
QAとQBの条件が求まります。
Q=QA+QB
よりQAが求まります。
QBを求めてもよいです。
ここからE3を計算します。
6)の電位差= E3dです。

6)までの計算を再度
し、求めてもよい。
6)から電気容量が求まるので
電気容量から求めます。
d.

Cが与えられ、d,ε0が使えません。
Cで代用するので、
Cを求めておきます。
公式として覚えておきましょう。
忘れても、導けるようにしておきましょう。

並列の電気容量は和で
求めるのが効率的なので
利用します。
問題文の誘電率は
(1+k)ε0 ということです。

2)
回路で演習しますが、
S閉じた直後は、電荷0
なので、
コンデンサの電位は
Q/Cより、0になります。
V = RI+0より電流を求めます。
3)
十分時間がたつと、
コンデンサの電荷が移動しなくなるので、
コンデンサを流れる電流は0
になり、回路を流れる
電流は0になります。
抵抗の電圧=0より
電荷を求めます。
電気容量は1)で計算済です。

1)でそれぞれの電気容量は出しています。
電圧もVなので、
比を計算します。

誘電体を挿入する時の
電気力を求めます。
エネルギー保存則を利用するのに
必要な仕事、エネルギーを求まめます。
5) 電池の仕事は電荷の変化×起電力
6) コンデンサの静電エネルギーの変化です。
V固定なので、この形です。
直接1/2QVでも良いです。
5)の計算結果を用いると楽です。

エネルギー保存則を利用します。
まず外力の仕事を求めます。
回路に抵抗があるので、
本来は抵抗の仕事も考える必要があります。
以下の分
ゆっくりと𝒙+𝚫𝒙まで移動させた
⇒電圧V一定になるので、
WRは考えません。
5),6)もV一定として
計算しています。
従って、
外力の仕事が求まり、
外力を求めます。
想定通り、
外力は負で外側に引っ張る力になり
電気力は大きさ同じで
向き反対なので、
+x方向になります。
ここで、終わりですが、
電池をはずしてxを移動させる問題もあります。
計算してみるとよいでしょう。
e.

コンデンサの電荷状況を求めます。
1.外側に電場=0⇒外側の電荷0
2.向かい合う電荷は大きさが等しく符号逆
のルールで図のようになります。
求まった電荷から電場の大きさが求まります。

基本問題のb.のように求まることもできます。
例としてAとPの間E2が和で求まります。

Pでの電場の大きさは、
Aが作る電場とBが作る電場の和です。
E2+E3ではありません。
電気力を求めます。

Pに働く外力は、2)の電気力と、重力です。
運動方程式を求めます。

加速度一定より
運動エネルギーの差=外力の仕事や
速度差の公式などで
Bでの速度を求めます。

Bにたどり着かないのは、
VBが存在しなければよいので、
√内が<0が条件になります。
f.
電気引力での単振動の問題です。
[1]


電気引力は F = 1/2 QE です。
1) ~ 3) で、外力の仕事から求まる問題です。
1) 、2)を求めます。

外力を求めて、電気引力を求めます。
F = 1/2 QE になってます。
[2]

Qを求めます。

電池を取り除くので、
Qは変化しません。
電気引力は[1]を利用します。
Qが変化しないし、
幅に関係ないので
一定になります。
ばねの伸びの軸から
間違えないように求めます。
つり合いの位置から
つり合いのばねの伸びをもとめて
運動方程式を求めます。
単振動になりました。
単振動の問題を
6) 7) で解きます。

6)
単振動でずれがあるので、
kでくくります。
中心を求め周期を計算します。
7) 位置確定パターンなので、
求めているのは、逆の最大値のことなので、
振幅の2倍が答えになります。
[3]
[2]までで終わる問題が多いですが、
V変化なしの問題まであります。
V変化なしの場合は、電荷が変わることになります。

y位置での引力を計算します。
3) 4)同様に、引力が求まります。

8) の計算結果から
評価します。
そのまま振幅を求めることは
難しいです。
yの評価から、
今回の電気引力と[2]の電気引力の
大きさの評価が来ます。
ばね、重力は電圧の変化に関係ないので、
降下位置の評価ができます。