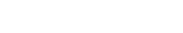電気回路
回路問題の演習です。
回路問題では、
まずキルヒホッフの法則を利用して方程式を立て、解いていきます。
また、使用されている素子の種類によって、電圧やエネルギーの求め方が異なります。
基本的な解法の流れは以下のとおりです。
-
回路方程式を立てる(キルヒホッフの法則を適用)
-
必要に応じてエネルギー保存則を使う
この方法は直流回路でも交流回路でも共通して使えます。
キルヒホッフの法則

回路問題において、キルヒホッフの法則は極めて重要です。
第1法則(電流則)
分岐点では、流入する電流の総和と流出する電流の総和が等しくなります。
電流は途中で消えたり生まれたりすることはありません。
第2法則(電圧則)
閉回路を一周すると、電位は元に戻ります。つまり、回路を一周したときの電圧の総和は 0 になります。
ただし、各素子にかかる電圧には向きがあるため、符号を正しく扱う必要があります。
第2法則を利用する際は、以下のように表記できます。
・各素子に三角形マークを描き、向きを統一して計算する
・式の書き方例
∑(起電力)=∑(素子電圧)
∑(右側)=∑(左側)
∑(ある点からその点までの全電圧)= 0
問題によって解きやすい書き方で式を立てればよいです。
このサイトでは、第2法則を回路方程式と呼び、解法の基本として扱います。
素子の電圧、エネルギー

出題頻度の高い素子の
電圧降下とエネルギーは、定義として覚えておくと良いでしょう。
コイルについては、起電力として扱う場合もあります。
しかし、抵抗やコンデンサと同様に「電圧降下を生じる素子」として扱ったほうが、
問題を解きやすくなります。このサイトでは、この方法で統一します。
なお、参考書などでコイルの式に負号が付いている場合は、
それを起電力として扱っていると考えてください。
過渡現象

直流回路の問題でよく出題される過渡現象の扱いについて説明します。
覚えにくいポイントとして、
電圧が 0 の場合でも、電流が 0 にならないことがあるという点があります。
電圧が 0 ということは等電位であり、この場合でも電流は流れることができます。
このようなときは、その部分を導線として扱い、素子を消して考えて構いません。
一方、電流が 0 の場合は、キルヒホッフの第1法則により、周囲の回路にも影響を及ぼすことがあります。
この関係を理解しておくと、回路解析がスムーズになります。
具体的な挙動や解法は、演習問題を通して確認していきましょう。
コンデンサ回路

コンデンサを含む回路では、十分に時間が経った後(定常状態)において、電流 = 0 となります。
このとき、多くの問題ではコンデンサの電荷分布を問われます。
コンデンサを含む回路を解く際は、まず次の手順を踏むと効率的です。
-
電荷分布の設定
各コンデンサに蓄えられる電荷を変数として設定します。 -
回路方程式の作成
キルヒホッフの第2法則を用いて電圧の関係式を立てます。 -
電荷保存則の利用
接続部で、電圧の変化がない場合は常に保存則が成立します。
これでも、なにか解けない場合は、エネルギー保存則、
回路全体のエネルギー収支を考えることで、求められる場合があります。
交流回路

交流回路の場合です。
交流回路では、電圧・電流は
Sin、Cosの関数で時間とともに変化します。
直流回路のオームの法則に対応する概念として
インピーダンスZ があり、これを使えば
V = ZI
の形で扱えます。
交流回路の問題も
直流回路と同様に、キルヒホッフの法則を適用して回路方程式を立てて解きます。
交流回路では電力が時間とともに変化するため、そのままでは電力を求めにくいです。
そこで 実効値(RMS値)を用い、平均電力を
P = Ve×Ie
として計算します。
交流回路 抵抗、コンデンサ、コイル



交流回路の例として
抵抗とコンデンサとコイルの
電流と平均消費電力を求めてみます。
・抵抗の場合
回路方程式を作成して
インピーダンス、平均電力を計算します。
(抵抗単素子の場合レジスタンスと呼ぶことがある。)
平均電力から実効値を求めることができます。
・コンデンサの場合
直流回路と同じように電荷を設定し
回路方程式を作成します。
電流の定義 I = dq/dt より電流を計算します。
Sin,Cosの微分については、単振動で利用しています。
電流、電圧からインピーダンスを計算します。
(コイル、コンデンサ単素子の場合リアクタンスと呼ぶことがある。)
平均電力を計算します。
0となりコンデンサは交流の場合、消費しないことになります。
・コイルの場合
回路方程式を作成して
インピーダンス、平均電力を計算します。
三角関数の周期における平均値の計算は、この後のセクションで扱います。
交流回路の解析では、微分や積分が必要となります。
微分・積分を使わない方法としてベクトル図を用いる解法もありますが、
ベクトル図を丸暗記するよりは、三角関数の微積分を理解して使えるようにしたほうが有用です。
特に、数Ⅲを学習している方であれば、Sin、Cosの微積分は使えるはずです。
また、積分では積分定数が現れますが、この場合は 0 として問題ありません。
本サイトでは、ベクトル図による解法は扱わず、微分・積分を用いた方法を採用します。