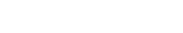交流回路
演習解説
これらはすべて標準的な問題です。
交流回路の解き方を、しっかり基礎から身につけていきましょう。
最初は微分や積分、三角関数の合成などが難しく感じられるかもしれません。
でも大丈夫。何度も繰り返していくうちに、必ず手が動くようになります。
できる自分を信じて、一歩ずつ進んでいきましょう。

交流回路の問題では、多くの場合、
インピーダンスを計算させる問題が出題されます。
基本式は V=ZI ですが、
ここでの V と I は最大値を求める必要があります。
最大値の求め方については、各問題で演習します。
a.

素子の直列回路です。
交流の問題ですが、
直流と同様に回路方程式を立てます。
コンデンサが含まれる場合は、
コンデンサの電荷と電流の定義式が必要です。

問題で与えられた電流の式を代入します。
電荷は、電流を積分して求めます。
計算が終わったら、
sin とcos の項に整理します。
これが問題で与えられるV0sinωtになるので、
sinの加法定理での合成を行います。

三角関数の合成を行います。
三角関数の合成が不安な場合は、
もう一度数学の参考書などで確認してください。
合成を行うと、sin
の式で等号が成り立ちます。
すべてのt で成立するため、
係数と位相が一致する等式ができます。
ここまでくれば、交流回路の解法は完了です。
あとは、問題に沿って順序立てて解答していきましょう。
1)

I0 , tanΦの計算です。
最後に計算した式から値を入れて解答します。
2)

式は ω を含む形となります。
微分が得意な場合は、微分して増減表を作成し、
最大値を求めても構いません。
しかし、この式は定数 ÷ g(ω) の形になっているため、
微分せずとも g(ω) が最小となる ω を求めれば、最大値を得られます。
また、式の形から g(ω) > R であることが分かるので、
g(ω) の最小値を求めることができます。
3),4)

3)抵抗の消費電力を求めます。
電流が交流であることを
忘れないようにして下さい。
sin2乗の時間平均は1/2です。
4)3)の結果に2)の結果を代入します。

抵抗での消費電力の時間平均が、2)の時の半分になる
は、4)の解答の1/2ということです。
この時のωを頑張って計算します。
ω > 0 なので、解が2個に定まります。
間違えないように計算しましょう。
ここで、電流I が最大となるときの角周波数ω を共振といいます。
また、Δω は半値全幅(半値幅、帯域幅とも呼ばれる)といい、
この値は共振回路の性能を評価する際に利用されます。
b.

コイルとコンデンサが並列の回路の問題です。
並列部分の電圧が与えられています。
回路方程式をたてて、電流を求めます。
2) , 3)


回路のインピーダンスを求める問題です。
インピーダンスはV = ZIから計算します。
2) ではまず、I(電流)を求めます。
キルヒホッフ第1法則より計算します。
3) 回路の電圧を求めます。
基本的な計算方法は1)とほとんど同じです。
まず、回路方程式をたてます。
三角関数の合成より、最大値を求めます。
2) , 3) よりインピーダンスを計算します。
最後まとめていますが、√前に係数として
出していても良いです。
4)

iR=0となるωを求めればよいことになります。
c.

ブリッジタイプの交流回路問題です。
ブリッジの電流が常に 0 であるため、
A点とB点は常に等電位になります。
また、LR側の電流、RC側の電流は
変わらない事になります。
この点に注意して解きましょう。
まず、回路方程式を立てます。
問題で与えられた電流i1 を代入して計算します。
全体の電圧が cos で表されているため、
三角関数の合成は cos の加法定理を利用します。

係数と位相の一致から、
I1,tanΦを求めます。
4) 5)

4) 解答で、Cを利用せよとあるので、
右側の閉回路で計算します。
5)右側と4)の結果から計算して
解答します。
d.

LC電気振動回路の問題です。
電荷と電流は単振動の挙動を示します。
計算の流れはおおむね同じなので、
解法の手順をしっかり押さえておきましょう。
[1]

[1] はRC回路です。
スイッチを入れた直後と、時間が十分経過したときに
何が起こるのかを、しっかり覚えておきましょう。
(3) 電源のエネルギーは、
コンデンサーに供給した電荷 × 起電力E で求められます。
[2]


LC回路です。
まず、初期の電荷から電流の向きを仮定します。
上の回路図のようになりますが、
このときコンデンサーの電流の向きが逆になることに注意してください。
交流のときと同様に、
コンデンサーの電流の向きを正とした回路図を描くと、下の図のようになります。
この場合、コイルの電圧は図のように表されます。
どちらの描き方でも構いませんが、
参考書では圧倒的に上の方式が採用されています。
上の方式では電流の向きが逆になることを忘れないようにしましょう。
間違えると、単振動の式になりません。

いずれの場合でも、
単振動の式を導くことができます。
あとは初期条件から電荷や電流を求めます。
今回の条件は
初期電荷Q0、初期電流0
なので、これは「位置確定パターン」に該当します。
したがって、直接 qが cos になる形で解いて構いません。
あとは問題文の指示に従って計算すればOKです。
もし単振動の考え方がまだあやふやな場合は、
単振動項目を演習しましょう。
4),5),6)

4) 単振動の係数の関係式からωを求めて
周期を計算します。
5)電流の最大値はiの式から求まります。
6) コイルの電圧は電圧の式から
計算します。同様にコイルの
エネルギーも計算します。
交流回路の問題は
1)~3)のように
インピーダンスが求められれば
問題はないでしょう。
頻度とすると、4)の
LC共振回路のほうが
よく出題されることが多いようです。
交流回路が出題されたときに
慌てないで得点することも大事なので
参考書含め解けるようにしておくとよいでしょう。
交流演習問題