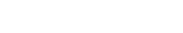直流問題 解説
直流の分野ですが、回路そのものではなく、
関連する問題やテーマを扱います。
いずれも標準的な問題です。
c.

オームの法則を電子論の観点から考える問題です。
電流の定義として、電子は負の電荷をもつため、
電子の動きと電流の向きは逆になります。
また、抵抗率の定義は間違えやすい部分ですが、
抵抗そのものについては
「導線が太いほど小さくなり、長いほど大きくなる」
という性質は感覚的に理解できると思います。
したがって、式の意味も自然に理解できるでしょう。
[1]

電子の運動方程式から加速度を求めます。
電子に働く外力は電場による力です。
この電場は、電圧との関係から求めることができます。
平均速度は、時間t0ごとに運動エネルギーが完全に失われることから、
電子の速度はt0まで加速された後、0になります。
このときの速度変化はグラフのようになるため、平均速度は1/2(v(t0)+0)で計算できます。

電流は、単位時間あたりの電荷の移動量として定義されます。
時間 t0の間に移動する電荷量を、図のような小さな円柱で考えます。
このとき、電子の数はn×体積で求められるので、そこから電流を計算できます。
さらに、電流と電圧の関係をオームの法則の式と比較することで、抵抗値を求めることができます。
最後に、抵抗値と抵抗率の関係式を用いて、抵抗率を導きます。
[2]

[3]

数値計算問題です。計算ミスをしないように注意しましょう。
特に、原子量の単位は kg ではなく g である点に注意してください。
また、mol の定義や扱い方を忘れてしまった場合は、必ず確認しておきましょう。
d.

電流とホール効果に関する問題です。
電流については、抵抗力によって一定の速度に達することを利用して求めます。
その他の部分は前問と同様です。
自由電子の運動方程式では、外力として「電場による力」と「速度に比例する抵抗力」を考えます。
一定速度となるときは、加速度 = 0 となります。
4)

数値計算問題です。計算ミスに注意しましょう。
消費電力 P=VI は、1 秒あたりのジュール熱を表すことに注意してください。
また、抵抗値が大きくなる理由を問う問題は頻出ですので、必ず覚えておきましょう。
[2]

ホール効果の問題は定番ですので、しっかり覚えておきましょう。
電子の運動では、ローレンツ力と、電子がたまることによって生じる電場が釣り合うことで、一定の速度が決まります。
特に電子は電荷が負であるため、速度の向き、ローレンツ力の向き、電子の蓄積によって生じる電場の向きに注意してください。