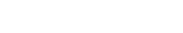電位と電場
問題解説
a・b・c は必須問題です。
d は標準問題になります。
e は電場の基本公式に関する問題なので、
こちらも必須です。
まだ慣れていない場合は、
繰り返し学習してしっかりと身につけましょう。
電位と電場は、
今後の物理学習でも頻出・重要なテーマですので、
早めに理解を固めておくことが大切です。
a.
電位・電圧(電位差)を求めるドリル問題です。
計算にあたっては、
キルヒホッフの第2法則を
利用することも可能ですが、
ここでは
「電位を意識して電位差を求める」
という練習を重視してください。
式に頼らず、
感覚的に電位の変化が
捉えられるようになると、
電気の理解が
一気に深まります。
すべての問題を暗算で解ける
レベルまで演習を重ねましょう。

(1)
電位の軸を作ります。
アースは0です。
三角形の向きに従って
電位を計算して
書き込みます。
Pの電位5Vになります。
(2)
(1)同様に電位の軸を作ります。
Pの電位は―10V
電位で、左側=右側から
Vx = 5Vはわかります。
(3)
電位の軸を作りますが
アースがありません。
低い位置を電位0として
軸を作りましょう。
(2)と同様です。
(4)
回路の中に
小さい回路が
あります。
が、
電位は同じです。
電位の
左辺=右辺と
小さい回路での
左辺=右辺
を組み合わせて計算します。

(5),(6)は似ていますが
違います。
(5)はPの分岐があります。
Pに電位差が無いので、
Pの位置は等電位です。
素子が無い線上は等電位です。
3本で電位の式を作り、
Pによる小さい回路2個分
を考えて計算します。
(6)
3本の電位を作ればよく
求まるところから
求めます。

(7)
アースが上と下にあります。
2個の軸があると思えば
良いです。
素子が無い部分は等電位なので、
10 = Vxで
赤の電位が求まり、
Vyも求まります。
(8)
電位差0があります。
電位差0は電位=0ではなく
等電位ということになります。
PとQの電位は同じです。

軸の高さは同じになります。
Vy=0になります。
Vxの向きが横になってるので、
縦にします。
後は2軸の等式から
求まります。
b.

この問題文を
理解します。
等電位面の線は曲線になっていますが、
曲線間の電位差はVです。

各位置の電位差は線間の個数を
数えればよく、
電位軸を作成できます。
(1)は求まります。

等電位面に垂直になるよう線を
描きます。

密集しているところが大きさ大になります。
電位の大きさではありません。
密集具合が同じような場合、
電位差/距離で実際に計算して
判断します。

外力の仕事 = 位置エネルギー差
力学でのエネルギーです。

電位の軸を参考にして
符号に気を付けて
計算します。
W(DA)はそれぞれ計算して
和を求めるのではなく、
位置エネルギーは経路に
関係ないので、
直接電位D,Aから求めます。
電気力がした仕事を求められる場合は
WE = ―ΔUなので、

(5),(6)は
力学的エネルギー保存則を利用します。
運動エネルギーの差が
位置エネルギーの差でも良いです。

AとBで力学的エネルギー保存則
から計算します。

無限遠への到達は、
無限遠で、
運動エネルギーがあれば
よいことになります。
無限遠とDでの
エネルギー保存則から範囲を
求めます。
無限遠での電位0は問題分よりです。
無限遠での電位0なので、Φ3は負
なので、√の中にマイナスがあるのは
正しいことになります。
c.


電場の大きさを求める問題です。
電場の大きさは、
電位の傾きです。
1),2)はほぼ傾き一定の電位になるので、
傾きを求めることになります。

外力の仕事=位置エネルギーの変化
から求めます。
d.

一様な電場の大きさを
求める問題です。
この問題では、
電場の方向が明示されていないため、
慎重に問題文を
読み取る必要があります。
空間に3つの座標軸(x, y, z軸)が
示されていることから、
「各軸方向に電場があるのではないか?」と
予測を立てながら解くと
正解に近づくことができます。
また、一様な電場であることから、
各軸方向の電場も
それぞれ一様(一定)であると
判断できます。

1)~3)は、
外力の仕事=位置エネルギーの変化から
電位差、仕事を求めることができます。
求める表現を正しく読み、
正負を間違えないように
計算します。

電位差、距離から
電場の大きさが
求まります。
各軸の電場を
求め、
電場の大きさを求めます。
1)~の問いもヒントになり
想定通りもとまりました。
e.

球の表面積、体積です。
暗記するものですが
イメージとして
覚えておきましょう。

ガウスの定理より求めます。
電場の大きさは、
単位面積当たりの本数
だから、
電気力線の本数は
E×Sです。

点電荷による電場を求めることができます。
ここから、
クーロン力も計算できます。
また、クーロン定数は
真空の誘電率(真空率)を
使って表現されることがあり、
これは大学入試でもよく見られます。
したがって、
「クーロン定数 = 1 / (4πε₀)」の
形でも表現できるように、
しっかりと覚えておきましょう。

問題の順番で
各情報を求めて
ガウスの定理
N =Q/ε0
から電場の大きさを求めます。

対称性より
上面の電場と下面の電場は同じになります。
同じ方法で、
電場の大きさを求めます。