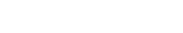電磁誘導
問題演習解説
標準問題:a, b, c, e
応用問題:d, f
これらは、基本問題の応用になります。
間違いが多い場合は、
基本問題の復習をしてから
取り組んでみてください。
特に f は、ベータトロンに関する
自己誘導電場の問題であり、
少し難易度が高めです。
a.
[1] 1)~5)
基本問題になります。
間違えないように計算しましょう。
計算方法がよくわからない場合は、
基本問題の復習をしてみましょう。


[2] (5)

導体棒2に電流が流れることで
力が発生して、導体棒2が動き出します。
力の向きは、+x方向です。
導体棒2が導体棒1に衝突しないので、
v1 > v2 が成立します。

6)
力を書き出して、運動方程式を作成します。

[3] 7),8)
運動方程式に代入して計算します。
ジュール熱はRi^2で計算します。


b.
1)

PQに電流が流れることから、
導体棒に力が発生します。
この電流による力を求めることになります。
電流は回路方程式から求まります。
この時,導体棒は停止しているので、
誘導電力は発生しません。
力の向きは、 +x方向になります。
2)

3)

導体棒がv0の時、誘導起電力が発生します。
これを含め回路方程式を求めます。
ここからI0を計算します。
v0を求めるのに、V = Eになるので、
I0=0とするのは、この問題では
間違えとなります。
もし、I0=0にすると、電流による力=0に
なります。
この問題では、摩擦力があるので、
このままでは、摩擦力により速度0に
なってしまい、問題との整合性が取れないことになります。
4)

一定速度での運動方程式を
求め、3)の結果を含めて
計算するとv0が求まります。
c.
[1] 1)~3)


導体棒が回転する場合の
誘電起電力の復習です。
向きにきをつけて
計算します。
[2]

4) 電流が流れる方向から
導体棒の力の向きがわかります。
ここから、答えは、反時計回り
dになります。
5) P2の誘電起電力を求めて
回路方程式から
電流を計算します。

6) P2の導体棒に加わる力は
電流による力だけなので、
この力が=0だと
等速運動になります。
この状態が、一定加速度になるので、
誘電起電力が左右同じ時が
答える時の状態になり、
電流=0の時になります。
ここから、ω'を求めます。
7)電流=0なので、消費電力も0です。
d.
1)

運動量の変化 = 力積
を利用して速度を求めます。
力積を計算することになります。
直接求められないので、
逆から考えていきます。
力積=力×時間
力⇒電流による力
電流⇒誘電起電力
の逆順で求めていきます。
まず、誘電起電力です。
導体棒がありますが、
停止しているので、
導体棒の運動による
誘電起電力はまだ0です。
この状態では、
磁束密度が変化する事で、
誘電起電力が発生します。
誘電起電力を求めます。
誘電起電力から電流を求めます。

電流による力を求めます。
Bが時間変化する事を
忘れないようにしましょう。
次に、時間変化する力の力積を求めます。

力が時間変化する場合は
力積は積分になり、計算します。
積分部は三角形の面積になります。

力積が求まったので、
運動量変化からt=t0の時の
速度が求まります。
2)

3)

t>t0では、磁束密度の変化はなくなるので、
1)での誘電起電力=0になります。
今度は、導体棒がx方向に動くので、
導体棒の運動による誘電起電力が発生して
力が発生します。
この力での力積を求めます。
手順は1)とおなじです。
時刻tでの速度をvとして計算します。

力の向き、
Δtでは、力積はそのまま積で良いです。
Δx = vΔt を利用して計算します。
4)

3)の結果が一定なので、
運動量の変化Δ(mv)、変位Δxを
そのまま計算して停止位置を計算します。
e.
[1] 1)

磁束密度が変化する場合の問題です。
向きに注意して計算しましょう。
スイッチが開いているので、
電流は流れません。
2)

電流0なので、
Qの電位は常に0です。
[2] 3)

スイッチを閉じると
電流が流れます。
回路方程式を計算して
電流を求めグラフを描きます。
4)

電流向きがわかるので、
力の向きは中心方向になります。
5)

電位をG基準で求めるほうが
間違いにくいです。
計算してグラフを描終了です。
f.
ベータトロンの問題です。
誘導電場を求める際
戸惑ることもあるので
実践しておきましょう。
1)

円運動するので、
運動方程式を作成します。
力はローレンツ力になります。
vが1個消去され運動量が計算できます。
2)

磁束の変化により、
誘導起電力が発生します。
電位が発生しているから
電場があります。
誘導起電力は1周での電位なので、
電位= 電場×距離(電場一定なら)
なので、電場が求まります。
そもそも電場が発生していることにより
誘導起電力が発生するのですが、
いずれにせよ電場が計算できます。
3)

電場があるなら、力が発生します。
接線方向の運動方程式から
運動量の変化が求まります。
運動量の変化=力積でも
良いでしょう。
4)

半径が変更しないので、
常に運動方程式は成立します。
Bが変化した時、vも変化したとします。
運動量の変化が求まり、
3)と比べてΔBが計算できます。
ベータトロンの問題は大体同じような
問題になるので、押さえておきましょう。
電磁誘導の問題演習は終了です。
電磁誘導の求め方としては大体
このようなパターンとなります。
向きが間違うことなく求められるように
しましょう。
導体棒の問題は、
回路、力学と結びつけて出題が
されることが多いので間違えた場合、
よく復習しましょう。
・電磁誘導