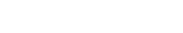電磁誘導
基本問題解説
必須問題 a. c. d. e.
標準問題 b. f.
間違えが多い場合は、
よく復習して、
計算できるように
しましょう。
前に戻って演習の
必要はありません。
電磁誘導でよく使う物理量の向きと大きさ

電磁誘導の問題は向きが重要です。
確実に覚えましょう。
大きさは、
親指の項目×B(親指以外の指)×l
です。
a.

平行移動導体棒の誘電起電力は vBlです。
向きは右手を図のようにして
P⇒Qの方向になります。

誘導起電力を電池だと思って
回路の問題として計算していきます。
電圧、電位から電流を求めます。

導体棒が磁束密度Bから受ける力を
計算します。
向きは、親指をiの方向に合わせて
求めます。

3)で導体棒には、
運動を妨げる方向に
力が発生しています。
(減速します。)
外力Fを加えて等速にするには
運動方程式より、
F = Fi になります。

導体棒が受ける仕事率になります。
等速なので、運動エネルギーの変化はありません。
従って、外力の仕事率PFを求めればよいことになります。
ジュール熱の表現からすると、
発生する起電力の仕事のほうがしっくりするので
起電力の仕事 Pv= Viを計算します。
回路を考えると、抵抗Rで発生するジュール熱PRと同じになります。
実際に求めるとすべて同じになってます。
ここでは、どの方法であってもよいです。
問題によっては、直接求めることが難しいこともあるので、
求められる方法の選択が必要です。
この問題a は電磁誘導の基本問題になるので、
間違えないようにしましょう。
b.

a.の復習になります。
導体棒に抵抗rが
あることを忘れないでください。
電圧の関係から
電流を計算します。

誘導起電力は同じです。
R2側を閉じると、
R2側に電流が流れる
回路ができます。
回路方程式、電流保存則より
計算すると電流が求まります。
閉回路で起電力を計算する方式
(レンツの法則)で行う場合
閉回路が2個あるので、
両側での起電力の和とするのは
間違えです。
あくまで、導体棒に起電力ができるので
スイッチにより起電力は変更しません。
c.

電磁誘導での、導体棒が斜面を運動する場合の問題です。
誘導起電力はファラデーの法則により求めますが、
磁束ΔΦ=BSに関して、速度も斜面方向なので、
面積は同じです。
磁束密度は、面積に対して垂直方向の成分になるので、
Bの斜面垂直方向は、Bcosθになります。
電磁誘導では、Bcosθとして問題を解くと考えやすくなります。
力については、斜面方向に直すことを忘れないでください。

1) 導体棒が上昇する条件を考えます。
まず、導体棒を置いた状況です。
導体棒には重力があり、斜面方向は下降方向で、
上昇しないことになります。
回路として考えると、
導体棒を置くと、導体棒に電流が流れます。
導体棒に電流が流れ、磁場がある場合、
導体棒に力が発生します。
この力を考えます。

導体棒に流れる電流をI、力をFiとすると、
Fi = IBlとなり向きは、左側になります。
Fiの斜面方向の力は、Ficosθになります。
図のまま、計算してもIBcosθlなので、同じになります。

上昇方向の力が発生することになり、
上昇する条件を考えると、
Ficosθ > mgsinθ
であれば、上昇することになります。
これを、まとめ計算します。

2)
状況をまとめて、終端速度になる現象を
考えてみましょう。
まず、導体棒が上昇すると何が起こるでしょうか?

導体棒が運動すると、
誘導起電力Vが発生します。
向きはP⇒Qです。
V = vBconθlとなり、
速度が上がると起電力は大きくなります。
一方、誘導起電力Vでの
電流を考えるとVが大きくなると
電流が小さくなることがわかります。
電流が小さくなると、導体棒の電流の力Fi
は小さくなっていきます。
導体棒の運動方程式を考えると

Ficosθが小さくなり、mgsinθになると
加速度0になり等速運動になることがわかります。
この時の速度をv0として求めることになります。
状況をまとめ計算します。

3)

4)
3)の結果が1にならない理由を考えます。
エネルギー保存則を考えると
電源のエネルギー=ジュール熱+位置エネルギーの変化
と考えられる(コンデンサー参照)ので、
位置エネルギーの変化を考えてみます。
位置エネルギーの変化Pgとして計算してみます。

単位時間当たりの仕事Wp = Fvを利用しています。
予想通りになるよう、計算していきます。
予想通り、残りは位置エネルギー分になっていることがわかります。
d.

導体棒が回転する時の誘導起電力を扱う問題です。
導体棒がレールを平行に運動する時と掃引面積が異なるので
磁束の変化も異なり、誘導起電力も異なります。
磁束の変化が扇型になることを覚えておけば、
誘導起電力は求まるので、公式的に覚えなくて良いです。
誘導起電力の向きは、以前と同じで、速度を親指に合わせればよいです。
1)
導体棒が運動する状況を考えます。
まず、スイッチSを閉じます。

回路ができ、電流がb⇒回転子中心に流れます。
中心から各導体棒を通り、a⇒電源に流れる
ループができます。
磁場中の導体棒に電流が流れると、
力が発生し、導体棒が動き出します。
力について考えます。

電流、磁場の方向から力の向きがわかります。
よって、導体棒が回転する方向はQになります。
2)
回転する導体棒の誘導起電力は、
上記説明通りです。
3)


導体棒が動き出した後について考えます。
導体棒の誘電起電力の向きは
中心方向になります。
導体棒は4本あり、それぞれの誘電起電力は
同じ角速度で動くので同じになります。
従って、図のような並列の誘電起電力の
回路になります。
その後、どうなるかを考えると、
回転をはじめ、角速度が大きくなっていくと、
誘電起電力が大きくなっていきます。
誘電起電力が大きくなっていき、電池の電圧と
同じになると、電流が0になるので、
力が0になります。
この状態が最終状態になります。
この状態を計算して、ω0を計算します。
4)
6本になると並列の本数が増えるだけで、
各誘導起電力は同じなので、
ω0は同じです。
各導体棒に流れる電流は異なります。
e.
1),2),3)

磁束密度が位置で変化する問題になります。
今までと同じように解くことができます。
RQの位置をxとします。
(SPの位置をxとしても同じ結果になります。)
PQ=bより、SPの位置はx-bになります。
RQ,SPの磁束密度B1,B2は、
B1=kx , B2 = k(x-b)
になります。
それぞれの誘電起電力V1,V2が求まります。
V1,V2の大きさは結果から V1 > V2とわかります。
従って、電流はQ⇒P方向になります。
これをまとめて、1),2),3)を計算します。

3)は抵抗と起電力だけなので、
PE = Viでも同じです。
4),5)

電流、磁場により導体棒に力が発生します。
全問同様に、RQ,SPでの力を計算します。
SR,PQ間にも力は発生しますが、
同一x位置では同じ大きさで向きが
逆になるので、相殺され0になります。
コイルにかかる力はRQ,SPの位置だけになります。
それぞれ計算して、結果から、F1>F2と
わかるので、全体の力は負になります。
この力がかかっている状態で、
一定速度となる外力Foを計算して、
仕事率も計算します。

f.

磁束密度が時間変化する問題です。
ファラデーの法則による
誘電起電力を使う問題です。
面積は常にSなので、
誘電起電力の大きさは、
磁束密度の時間変化の微分(傾き)×S
になります。
この問題は、大きさよりも
向きに注意が必要です。
誘電起電力+の場合は右ねじの方向
誘電起電力-の場合は右ねじの方向の逆
になります。
この問題をよく理解しましょう。
1),2)
ここでは、
1),2)一緒に考えて、
t=t0の時として解答することにします。

誘電起電力は電池だと
考えてよいので
問題をまとめると上図のようになり、
Qの電位を求めることになります。
誘電起電力の正負により
電位の向きも変わることに注意してください。
いずれの場合もPの電位は0なので、
Qの電位は ―Vになります。
誘電起電力を求めます。


誘電起電力の計算用に
まず傾きを計算します。
誘電起電力を求めます。
ここでは、右ねじ方向を+とします。
この時点で、1)は求まります。
向きは、-なので、P⇒Qになります。
2)はQの電位なので、
ーV のグラフを作れば良いことになります。

グラフの向きを間違えた場合
誘電起電力の向きと
答えるべき量の正負を
間違えないよう復習してください。
切り口が左になると答えも変わってくることも
忘れないようにしてください。
この問題は、暗記では解くことが難しく
向きを含めて理解することが必要です。
正しく理解すれば、間違いはほとんどしないので
いくつか似た問題をさがして解くとよいでしょう。
基本問題は終了です。
よく主題されるパターンなので、
この問題と、演習問題をやり
他の問題いくつか実践してみましょう。
電磁誘導は、理解すれば、
ほとんど同じ形式で出題されるので
得点源です。