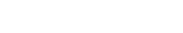円運動
基本問題解説
円運動基本問題の解説です。
すべて、必須問題です。
運動方程式を立てる際は、
加速度の向きや大きさがすでに決まっていることを意識しましょう。
特に加速度の向きが力の向きと一致しない場合もあるため、注意が必要です。

円運動では、
加速度は常に中心方向(向心加速度)に向いていることを意識して、
運動方程式を立てましょう。
*等速円運動でも非等速円運動でも、物体が円運動している限り
加速度の式は同じ
a.

水平面での円運動で、中心方向の外力は
ばねの弾性力です。
ばねの長さがl1なので、ばねの伸びは
l1-l0となり弾性力は k(l1-l0)になります。
2) 1)の運動方程式よりl1を計算します。
3) 等速円運動なので、 ωT = 2πになります。
4) l1が存在すれば、運動方程式は成立します。
ωがどんどん大きくなると、
l1は大きくなり∞となる時が解答するときになります。
b.

1)、2) は運動方程式を作成する問題です。
水平方向では円運動をしており、鉛直方向では静止しています。
円運動の半径を計算し、水平方向に張力
TT の成分を分解して考えましょう。
3) 鉛直方向から、張力が求まります。
4) 等速円運動から周期を計算します。
c.

円運動の解法
・各点の運動方程式(中心方向)を求める。
・状況の力学的エネルギー保存則を求める。
(力学的エネルギー保存則は、摩擦や非保存力がない場合に使える。)

円運動が成立しなくなる条件
張力や垂直抗力が0未満(負の値)になると、
実際にはその力が存在しないことになるため、
円運動は成立しません。
張力や垂直抗力が0以上であることが、
円運動が可能な条件になります。

1),2) P,Q点の運動方程式を作成します。
中心方向を正として、外力を分解します。

3) P.Qの力学的エネルギー保存則を求めます。
位置エネルギーの基準は、Pとしていますが、
Oにとっても良いです。
4)2式から N(θ)を求めます。

5) R まで円筒から外れることなく到達するためには、
物体が円筒の内側を常に接して運動している必要があります。
特に、最上点(θ = π)で円筒から離れないためには、
その点での垂直抗力 N(π) が 0 以上であることが条件です。
したがって、
N(π) ≥ 0 を条件に立式し、
初速度 v₀ の最小値を求めます。
d.

点PとQの運動方程式、力学エネルギー保存則を作ります。

離れる時は 垂直抗力N =0の時になります。
e.

円運動において、糸や棒におもりをつける問題では、それぞれ特徴が異なります。
-
糸の場合:
張力が負(=たるむ)になると、張力は実在しないため、
円運動が成立しないことがあります。
このため、張力が 0 以上であることが成立条件になります。 -
棒の場合:
たるむことはない(剛体なので圧縮にも耐える)ため、
おもりは常に円軌道上にあり続けることになります。
したがって、棒を使った場合は、張力の代わりに”棒が押す力(または引く力)”が常に作用し、
円運動が継続されます。
[1]

棒の問題なので、おもりが円軌道を外れることはありません。
Rにたどり着くのは、Rで運動エネルギーがあれば良いことになります。
力学的エネルギーをたて問題を解きます。
[2]
糸の問題です。 張力が負になると円軌道から外れます。

点Qでの運動方程式、
点Pと点Qの力学的エネルギー保存則から
張力を求めます。

2) 初速度と、円軌道上の点R(最上点)での張力を計算し、
おもりがそこまで到達できるかどうかを検討します。
その結果、張力が負になることから、
物理的にその地点まではたどり着けないことがわかります
(張力が負になる=糸がたるむため、軌道が維持できない)。
そこで、張力がゼロになった直後の運動に注目します。
張力がなくなった時点で、おもりに働く外力は重力のみとなるため、
その後の運動は放物線運動に移行します。
おもりが円の外側を通るか内側を通るかは、張力がゼロになる時点での速度によって決まります。
この判断のためには、たとえばθ = 90°(円軌道上の水平位置)での張力を求め、
そこで張力が正かどうかを確認するとよいでしょう。
T=0からcosθ=-2/3を計算して内側になることを確認してもよいでしょう。

たどり着くには、R点で張力が正になればよいので、
その条件から最小となる速さを求めます。