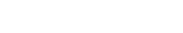力積問題演習
解説
これは、
力積に関する問題演習の解説です。
a~c は必ずおさえておきたい基本問題です。
d はやや難易度の高い問題ですが、
力積と力の関係を正しく理解するための良問です。
もし 解法が思いつかなかった という場合でも、
内容をしっかり確認し、
必ず解けるようにしておきましょう。
a.

運動量と力積の関係式についての解説です。
この式は、外力が加わり、
その結果として速度に変化が生じる場合に使用します。
立式の手順は運動方程式と同様で、
まず外力を見つけることが重要です。
その外力によって物体の速度が変化した場合、
運動量の変化後-運動量の変化前
= 力積になります。
力積を解答するときの注意点:
-
「力積を求めなさい」
→ ベクトル量として答える(符号を含めること) -
「力積の大きさを求めなさい」
→ スカラー量として答える(正の値で)
これらの違いに気をつけましょう。

1) 運動量と力積の関係式を作成します。
図を見ると、外力は x 軸負方向に
作用していることがわかります。
したがって、
運動量の変化 = 力積の関係式より、
―2mv= ―I となります。
問題文の力積の表し方が「大きさ」なのか、
「向き付き」なのかが問題文で曖昧なので、
―2mv = I
と書いても正解です。
重要なのは、
左辺(運動量の変化)が正しく書けていることです。
2) I = FΔt より
Fを求めます。
このFも曖昧なので、 F が負でも問題ありません。
-x方向が理解できていれば問題ありません。
b.

1次元の運動でない場合は、
運動量の変化や力積をベクトルで表します。
ベクトルの差の形式は図示しにくいため、
「運動量の変化後 = 運動量の変化前 + 力積」
の形で覚えておく方が図示しやすく、
変化前の終点から変化後の終点を結ぶと、
その向きが力積の方向になります。

1) 運動量の変化後=運動量の変化後+力積
を図示します。
2)力積の大きさを求めます。
数学の問題にある
ベクトルの問題で大きさを求めます。
内積の計算が苦手な場合は、
余弦定理を使っても構いません。
多くの解答例では
余弦定理が用いられていますが、
ベクトルの問題であれば、
ベクトルの大きさから直接求める方が自然です。
また、数学のテスト中に
余弦定理を忘れてしまった場合は、
以下のベクトルの性質を思い出しましょう:
|C|^2 = |a-b|^2
c.

運動量と力積の関係式から解答します。
変化後の速度は 停止 なので、
速度は 0 になります。
したがって、mv=I になります。
また、力積の向き は、
弾丸の侵入方向と 逆向き になります。
図を見ると、x軸の負の方向 です。
d.

摩擦力の問題では、
状況に応じて運動方程式を立てて対応してください。
静止摩擦力と動摩擦力、
摩擦係数と動摩擦係数、
さらに水平方向と鉛直方向を
区別して式を作ることが重要です。
もしまだできていなければ、
しっかり分けて考えるようにしましょう。
そうすることで、
摩擦の問題を安定して解答できるようになります。
1)、2) は静止しているときの状況です。
この場合の摩擦力は一定ではありません。
安易にμmg と書いている場合は、正しく修正しましょう。
1) 運動方程式から
f = F になります。
F はグラフから求められ、
原点を通る直線の式から
導き出すことができます。
2)静止摩擦係数を求める問題です。
この場合、
物体が動き出す条件が必ず存在します。
この時の摩擦力 f = μN です。
この流れを理解して解答しましょう。
この問題では、
時刻t=t0が動き出す条件にあたり、
その時の力F = F_0F=F0と読み取れます。
これにより、
摩擦係数を計算することができます。

3) 4) 動いているときの
運動方程式です。
この時の加速度をaとして
作ります。
動いているときの摩擦力は
μ'mgと一定になります。
問題は「AがFから受けた力積」
を求めるものです。
このとき、Fは一定ではないため、
力積は公式のように
積分で求める必要があります。
積分はグラフの面積を意味するため、
グラフ上で
三角形の面積を求めることで解答できます。
もちろん、
積分をそのまま実行して求めても
まったく問題ありません。
「力積を求めよ」という問題では、
符号(正負)に注意することが重要です。

4) やや難しいですが、
求め方は3)と同様です。
時刻によって摩擦力が変化することに
注意し、
静止摩擦力と動摩擦力を分けて考えて
求めましょう。
最後に向きに注意しましょう。

運動量の変化と力積の関係式を利用して、
時刻3t0 における速度を計算します。

t> 3t0の時でF=0となり
外力としては
動摩擦力のみが働きます。
最終的に物体は停止します。
その停止する時刻を求める問題です。
運動の前後の速度や摩擦力がわかっているので、
運動量の変化と力積の関係を用いて
解答するのが適切です。
関係式より時刻を求めます。
外力が一定になることから、
加速度を求めて時刻を出す方法も有効ですが、
ここでは「力積」を利用する方が、
問題の意図に沿った解法だと言えます。