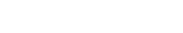ドップラー効果
頻繁に
出題されるわけではありませんが、
類題の多い重要な項目です。
ドップラー効果の出題には、
次の2つのパターンがあります:
1. ドップラー効果の公式を
利用する問題
→ 公式を正確に覚え、
パターン演習を重ねることで対応できます。
2. ドップラー効果の公式を
導く問題
→ 考え方がやや複雑で、
難関校でよく出題されます。
理解と論理的な組み立てが必要です。
まずは、
ドップラー効果の公式を
利用する問題から
取り組みましょう。
解説と演習を通して、
公式の使い方を
しっかり身につけることが
大切です。
ドップラー効果の公式

■ドップラー効果とは?
音や光などの波を発する物体と
観測者の相対的な運動によって、
波の周波数や波長が変化して観測
される現象です。
観測者の振動数は、
上の式で表すことができます。
細かく分けると4パターンになりますが、
覚えるべき式は1つで十分です。
上の図は、
その4パターンのうちの
2パターンを示しています。
覚え方には
さまざまな方法がありますが、
この方法が
間違えにくいと思います。
すでに自分に合った覚え方が
身についている場合は、
無理に覚え直す
必要はありません。
まず、
分数の形で式を表します。
このとき、
分子には観測者の情報を、
分母には波源の情報を入れる
ようにします。
速度の向きは、
必ず
「観測者から波源を見る向き」を
正(+)
と定義します。
この方向
(観測者から波源を見る方向)に対して、
観測者が動く場合は、
音速に観測者の速度を加減して分子に入れます。
同様に、
波源が動く場合は、
音速に波源の速度を加減して分母に入れます。
覚えるべきポイントは、
次の2点です。
-
分子には観測者の情報を、分母には波源の情報を入れる。
-
観測者から見た波源の方向を正(+)とする。
1.を忘れてしまうことがありますが、
このアイコンのイメージを使って、
忘れないようにしましょう。
公式を覚えて、
演習問題に取り組みましょう。
公式を導く問題

ドップラー効果の公式を導く問題には、
主に次の3種類があります。
-
波長(長さ、波の数) から導く問題
-
周期(時間差) から導く問題
-
波動の式 から求める問題
公式を問う問題は、
単に自分が知っている
公式の導き方を答えるのではなく、
多くの場合は
誘導形式で出題されます。
そのため、
3つの導出方法を覚えておかないと、
見慣れない形式が出たときに
戸惑ってしまう可能性があります。
この3種類の導出方法は、
しっかりと理解しておくとよいでしょう。
3つすべてのパターンが入った
問題集はあまり多くありませんが、
いずれかのパターンは
含まれていることが多いです。
このサイトの問題と、
手持ちの問題集を活用して、
バランスよく演習しましょう。
このパターンの説明については、
問題演習の中で扱うことにします。