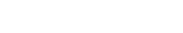光学
光学の問題は、主に「干渉」と「レンズ」に関するものがよく出題されます。
特に入試で頻出する分野なので、
解法のパターンをしっかり
身につけておくことが重要です。
ここでは、それぞれの問題について解説していきます。
光の干渉
反射

屈折率が異なる境界で、
屈折率が小さい媒質から大きい媒質で反射する場合、
光は固定端型の反射になり、
屈折率が大きい媒質から小さい媒質の場合、
自由端型の反射になります。
1)屈折率 小→大 の反射:固定端反射 位相はπずれる
2)屈折率 大→小 の反射:自由端反射 位相はずれなし
干渉

光の干渉では、
特に経路差のある反射光によって、
明るくなったり暗くなったりします。
入試問題では、ほとんどが
「明暗の条件を求めて答える」形式です。
明暗の条件は、
光路差や位相差のずれによって決まります。
明るい条件:2つの光が完全に一致するとき。位相差は2π×m(整数)
暗い条件:2つの光が打ち消し合うとき。位相差は πずれて、2π×m(整数)+π
ここで、位相差の 2π は「波長 λ」に対応します。したがって、光路差が
明るい条件:光路差Δ = λ×m
暗い条件 :光路差Δ = λ×m+λ/2=(m+1/2)×λ
になります。
暗い条件:2つの波が打ち消し合うとき。位相差は πずれて、2π×m(整数)+
基本的には経路差だけを考えればよいのですが、屈折率nのある媒質中では波長が短くなるため、光路差は
屈折率を掛けた値として考えます。
光路差は経路差×屈折率と考えてよいです。
空気中の場合、屈折率は1として考えます。
光の干渉 光路差
典型問題の光路差をまとめます。
基本的には暗記項目ですが、導き方もあわせて理解し、応用できるようにしておきましょう。
ヤングの干渉実験


図のように、2つのスリットと、離れた位置にスクリーンがあります。
スクリーン上には、明るい位置や暗い位置が現れます。
この場合、光路差を求める方法としては、ピタゴラスの定理を用いる方法と、
図に示した方法の2通りがあります。
覚えるという点では、図による方法の方が速く確実です。
回折格子

多数のスリットを作ったものを回折格子といいます。
光路差はdsinΘになります。光路差を求めることはそれほど難しくありませんが
強度などを求めたりと難問になりやすい問題です。いくつか典型問題を解いておくとよいでしょう。
くさび状薄膜

光路差は、
図のように 2d となります。
問題によっては、tanθ などを用いて d を表すこともあります。
この場合、
2つの反射光の間に
位相のずれが生じるため、明暗の条件が逆になることに
注意しましょう。
ニュートンリング


平凸レンズの下面で反射した光と、
平板ガラスの上面で反射した光が干渉し、
円状の明暗の縞(ニュートンリング)が現れる問題です。
この場合、
多くは光路差を導く問題が付随します。
確実に暗記する必要はありませんが、
導き方を含めて理解しておくことが重要です。
また、この問題でも
干渉の明暗条件が逆転することに注意しましょう。
平行薄膜干渉

屈折の法則を使うことも多いので、一緒に復習しておきましょう。
比の形より、屈折率の積で覚えることをお勧めします。


光路差は
屈折率 × (AB + BC) で表され、
これは図における AC′C の射影の長さになります。
この形を覚えておきましょう。
また、
光の軌跡で見たときに差がある部分は、
屈折による光路差であり、
光路差=0 となることに注意が必要です。
なお、この種の問題では、
屈折の法則を用いて入射角で表すことが多いです。

屈折による光路差を実際に計算し、
同じ結果になることを確認してみましょう。
このタイプの問題もよく出題されるので、
必ず一緒に覚えておくことが大切です。
また、OO′が共通の斜辺になることを意識しておけば、
図を見ただけで理解しやすくなります。
マイケルソン干渉計

半透過鏡と固定鏡を用いた干渉計を
マイケルソン干渉計といいます。
光は、一方は直進して鏡 M₁ で反射し、
もう一方は半透過鏡を透過して進行方向が変わり、
鏡 M₂ で反射します。
この2つの光の干渉を考えると、光路差は
両光線の往復距離の差になります
光学の干渉(明暗の問題)は、まず、ここまでの光路差、
明暗条件を正しく求められるようにしましょう。必須です。
しかし、入試では、ここからプラスアルファの問題がついています。
問題により何が出題されるかはわかりません。今までの経験などが必要です。
できる限り、演習ではここを含めるようにするので、どのような問題がでるか?
また解けるのか考えてみてください。 プラスアルファも解答できればかなり有利になるでしょう。
・光の干渉演習問題(基本)
・光の干渉演習問題